「自分のアイデアを形にしたくてプログラミングの勉強を始めたけど、環境構築でつまずいた…」
「サークルのホームページを作りたいけど、何から手をつけていいか分からない…」
「エラーの連続で、正直プログラミングは心が折れそう…」
こんにちは!『大学生のためのIT活用ラボ』を運営しているえいとです。
もしあなたが今、こんな風に感じているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。 実は、プログラミングの専門知識がなくても、自分のアイデアをアプリやWebサイトとして形にする方法があるのを知っていますか?
それが、今IT業界で大きな注目を集めている「ノーコード」と「ローコード」という考え方です。
この記事を読み終える頃には、あなたは「プログラミングができないから」と諦める必要がないことに気づき、「自分でも何か作れるかもしれない!」とワクワクした気持ちで、今日から新しい一歩を踏み出せるはずです。
最初に結論:プログラミング不要で開発できる魔法のツール
まず結論からお伝えします。
「ノーコード/ローコード」とは、一言でいうと「プログラミングの知識がほとんど、あるいは全くなくても、Webサイトやアプリを開発できる画期的な手法、またはそれを実現するツール」のことです。
両者の最大の違いは、その名の通り「コードをどれくらい書くか」にあります。
- ノーコード (No Code): コードを一切書かない。パズルのようにパーツを組み合わせるだけで開発できる。
- ローコード (Low Code): 少しのコードは書く。基本的な部分は自動で作って、こだわりたい部分だけコードでカスタマイズする。
これだけだと、まだイメージが湧きにくいかもしれませんね。 大学生活で一番イメージしやすい「学園祭の屋台準備」に例えてみましょう!
【大学生活で例える】ノーコードとプログラミングの違い
もしあなたが学園祭でタピオカ屋の屋台を出すとしたら、屋台そのものをどう準備しますか?選択肢は主に3つあるはずです。
1. プログラミング(フルスクラッチ):ゼロから設計して手作りする
これは、ホームセンターで木材や釘、ペンキを買ってきて、設計図を引き、自分たちでゼロから屋台を建設する方法です。 デザインも大きさも自由自在。世界に一つだけのこだわりの屋台が作れますが、相応の技術と時間、そして工具が必要です。これが、一行一行コードを書いてシステムを構築する従来のプログラミング(フルスクラッチ開発)のイメージです。
2. ローコード:DIYキットで半自動で組み立てる
これは、骨組みや壁など、基本的なパーツがセットになった「屋台DIYキット」を買ってきて、説明書通りに組み立てる方法です。 面倒な骨組みはキットが解決してくれますが、「看板のデザインは自分たちで描こう」「カウンターに可愛い飾り付けをしよう」といった一部のクリエイティブな部分は自分たちで工夫できます。 これがローコード開発です。基本的な機能はツールが用意してくれて、本当に重要な部分だけを少しのコードで実装するイメージです。
3. ノーコード:レンタル業者から完成品を借りる
これは、屋台のレンタル業者に連絡して、すでに完成している屋台を借りてくる方法です。 自分たちでやることは、お店の名前が書かれた看板を貼り付けるくらい。組み立ての手間は一切かからず、誰でもすぐに、しかも確実にお店をオープンできます。ただし、屋台の色を変えたり、形を特殊にしたりすることはできません。 これがノーコード開発のイメージです。用意されたパーツ(機能)をドラッグ&ドロップで配置するだけで、誰でもアプリやWebサイトが作れます。
どうでしょう?三者の違いが、なんとなくイメージできたのではないでしょうか。
なぜ今、こんなに注目されているの?
では、なぜ今このノーコード/ローコードがこれほど注目されているのでしょうか。 それは、社会全体の「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という大きな流れと関係しています。
簡単に言うと、「もっと色々な業務をデジタル化して、社会全体で効率を上げていこう!」という動きが加速しているのです。しかし、それを実現できる専門家、つまりITエンジニアの数はまだまだ足りていません。
そこで、「専門家でなくても、自分の業務に必要なツールは自分で作れるようにしよう!」という考え方から、ノーコード/ローコードの需要が爆発的に高まっているのです。
これは、私たち大学生にとっても他人事ではありません。 サークルのメンバー管理、ゼミの文献共有、就活の情報収集… 身の回りの「もっとこうだったら便利なのに」を、自分たちの手で解決できる時代が来ているということです。
実は僕自身、入学したての頃、慣れない環境や自分で履修を組み複雑になってしまっている影響で課題の提出をうっかり忘れることが本当に多くて悩んでいました。授業ごとにICTだったり、紙媒体だったりするので管理しきれなかったんですよね。
そんな時に出会ったのが、ノーコードツールの「Glide」でした。試しに「自分の課題管理アプリ」を作ってみようと思ったら、なんと1時間もかからずに完成してしまったんです。
やったことは驚くほど簡単で、Googleスプレッドシートに課題名と提出期限を一覧にしただけ。それをGlideに連携させたら、あっという間にスマホアプリの画面が出来上がりました。さらに、提出期限が近づくと自動でリマインドメールが届くように設定もできました。
この自作アプリを使い始めてから、課題の出し忘れは劇的に減り、結果として成績も向上しました。「こんなに簡単に、自分の悩みを解決できるのか!」と、初めて自分の手で “作る” ことの楽しさと便利さを実感した瞬間でした。
大学生が知るべきメリット・デメリット
便利なノーコード/ローコードですが、もちろん万能ではありません。 ここで、大学生の視点から見たメリット・デメリットを冷静に整理しておきましょう。
メリット
- 圧倒的な開発スピード: アイデアを思いついたその日のうちに、動くもの(プロトタイプ)を作れます。ハッカソンやビジネスコンテストで絶大な力を発揮します。
- 学習コストが低い: プログラミング言語の文法を覚える必要がありません。直感的な操作で開発できるため、プログラミングで挫折した経験がある人にこそ試してほしいです。
- 企画・アイデアを即座に検証できる: 「このサービス、本当に需要あるかな?」と思った時に、すぐ形にして友人に見せ、フィードバックをもらうことができます。
デメリット
- デザインや機能の自由度が低い: ツールの制約の中でしか開発できないため、「ここのボタンの色を少しだけ変えたい」といった細かなカスタマイズが難しい場合があります。
- 複雑な処理は苦手: 大量のデータを高速で処理したり、外部の特殊なシステムと連携したりするのは、やはりプログラミングに軍配が上がります。
- プラットフォームへの依存: 利用しているノーコードツールがサービスを終了してしまったら、作ったアプリも使えなくなるリスクがあります。
じゃあ、具体的に何ができるの?
ノーコード/ローコードで作れるものは、皆さんの想像以上に多岐にわたります。
- ノーコードツールで作れるもの:
- Bubble: InstagramやTwitterのような本格的なWebアプリ開発が可能。
- Adalo: App Storeで公開できるネイティブアプリ(スマホアプリ)が作れる。
- Glide: Googleスプレッドシートから数分でアプリを作成できる。サークルの名簿管理などに最適。
- STUDIO: デザイン性に優れたWebサイトを、コードを書かずに作成できる。
- ローコードツールで作れるもの:
- Microsoft Power Apps: ExcelやTeamsなど、普段使っているMicrosoft製品と連携した業務効率化アプリを素早く作れる。
- OutSystems: 大企業も採用する、高速なエンタープライズ(業務用)アプリケーション開発プラットフォーム。
ノーコード/ローコードの上手な使い方
私は、ノーコード/ローコードは「本格的な開発に向けた、最高の試作品(プロトタイプ)作りのツール」だと思っています。
サークル活動で使うちょっとしたアプリや、自分のアイデアを形にして誰かに見せたい時などには、間違いなく最適です。ゼロからコードを書くより圧倒的に速いですからね。
そして、もっと本格的なサービスを開発したい場合でも、いきなりコードを書き始めるのではなく、まずはノーコードでアイデアの骨子を作り、「この方向性でいけるか?」を試すための”施策”として活用するのが非常に効果的だと考えています。
これは、僕が専門で学んでいるロボットの電子回路設計と全く同じアプローチなんです。 回路設計では、いきなり基板にはんだ付けをして完成品を作ることはしません。まず「ブレッドボード」という、はんだ付けなしで手軽に部品を抜き差しできる実験用の板で回路を組み、「ちゃんと動くか」を徹底的に試します。そして、確信が持ててから初めて、本番用の基板を設計するのです。
僕にとってノーコード/ローコードは、まさにこの「ブレッドボード」のような存在。リスクを抑えながらアイデアを最速で試し、確信を持ってから本格的な開発(コーディング)に進む。この考え方を知っているかどうかで、開発の質とスピードは大きく変わってきます。だからこそ、コードを書ける情報系の学生も、この強力な武器を使わない手はないと思っています。
まとめ:君のアイデアをアイデアで終わらせないために
最後に、この記事の要点をまとめます。
- ノーコード/ローコードは、プログラミング知識が少なくてもアプリやWebサイトを開発できる手法。
- メリットは圧倒的な開発スピード。アイデアを即座に形にできる。
- デメリットは自由度の低さ。プログラミングとの使い分けが重要。
プログラミング学習は、車で例えるなら「エンジンの仕組みを理解して、自分で車を組み立てる」ようなものです。それは非常に価値のあるスキルです。
一方で、ノーコード/ローコードは「自動車の運転免許を取る」ようなもの。エンジンの仕組みは知らなくても、行きたい場所に素早く、簡単に行くことができます。
どちらが良い・悪いではなく、目的に応じて最適な手段を選ぶことが何よりも大切なのです。
次への一歩:まずは「作る楽しさ」を体験しよう
「少し興味が湧いてきたかも…」 そう感じたあなたに、今日からできる「最初の一歩」を提案します。
それは、無料のノーコードツールに登録して、テンプレートを触ってみることです。
特におすすめなのは、Googleアカウントがあればすぐに始められる「Glide」です。 まずはテンプレートから、日々のタスク管理アプリや、お気に入りのレストランリストなどを作ってみてください。自分の手で、驚くほど簡単のアプリが完成する体験は、きっとあなたの世界を広げてくれるはずです。
あなたの頭の中にある素晴らしいアイデアを、スキルの問題で眠らせてしまうのは、あまりにもったいない。 ノーコード/ローコードという新しい武器を手に入れて、ぜひ「創る側」の楽しさを体験してみてください。応援しています!
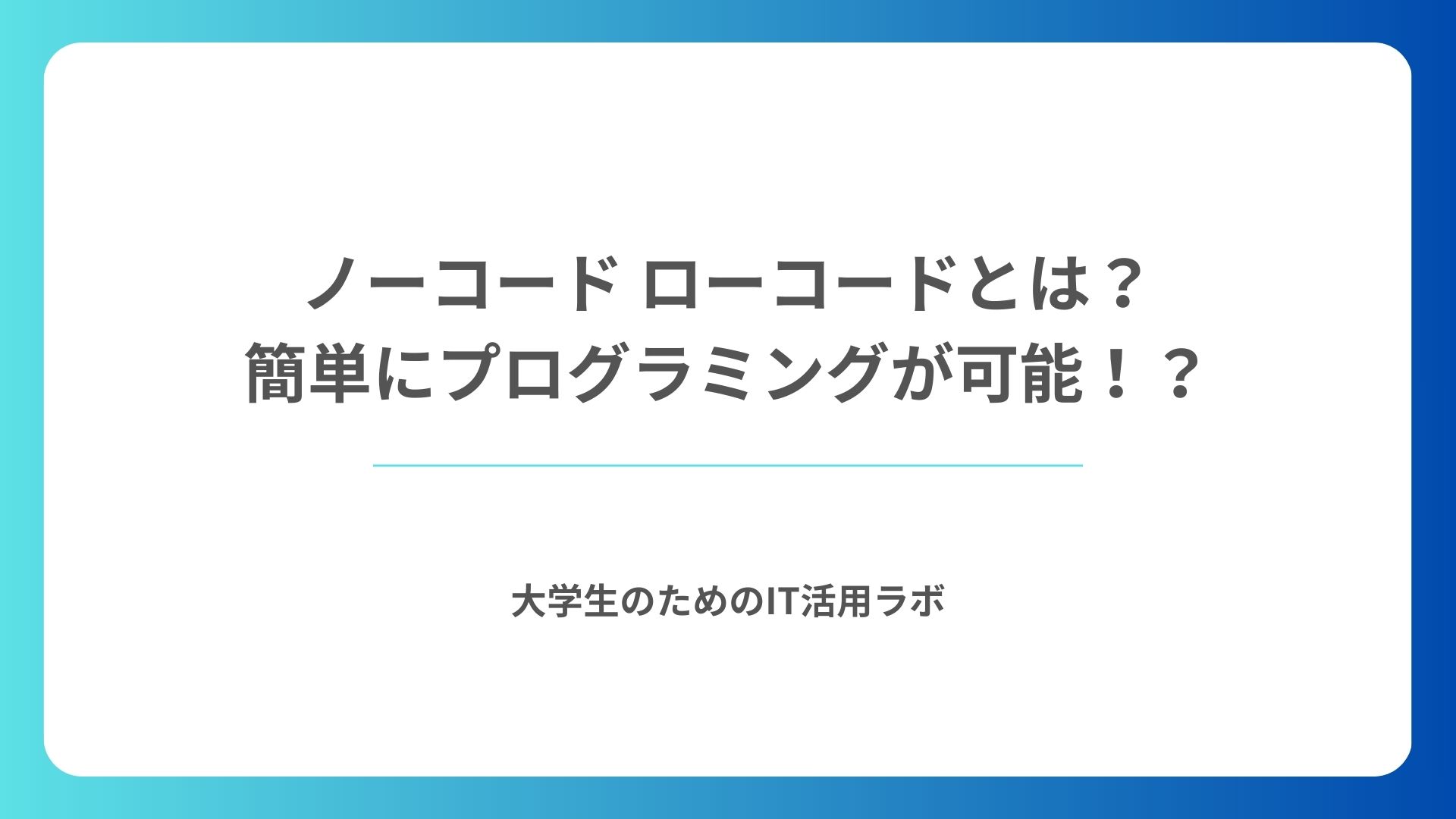


コメント