プログラミングの学習を進めると、多くの人が一度はぶつかる大きな壁。それが「オブジェクト指向」です。
「クラス?インスタンス?継承…?」 まるで魔法の呪文のような専門用語のオンパレードに、教科書を読んでもいまいちピンとこない…。あなたも今、そんなモヤモヤを抱えているかもしれませんね。
ご安心ください!この記事は、そんなあなたのための「攻略本」です。 オブジェクト指向とは何か、そして「なぜ」そんな考え方が必要なのか、その本質を、多くの人が親しんだことのある「RPG(ロールプレイングゲーム)」の世界に例えて、世界一わかりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはオブジェクト指向の本当の面白さとパワフルさを理解し、今後のプログラミング学習が何倍も楽しく、そして深くなるはずです。
オブジェクト指向とは「RPGのキャラクター設計図」である!
オブジェクト指向とは、一言でいうと、「現実世界の”モノ”を部品として捉え、その部品を組み立てるようにプログラムを作る」という考え方(設計思想)のことです。
これだけだと、まだ難しいですよね。では、RPGの世界で考えてみましょう。
もしオブジェクト指向がなかったら…?
もし、オブジェクト指向という考え方がなければ、ゲームに登場するキャラクターを100体作るには、100人分のキャラクター情報(名前、HP、攻撃力、使える魔法…)と、それぞれの行動(攻撃する、防御する、逃げる…)を、ひたすらプログラムに書き連ねていく必要があります。 これでは、少し修正するだけでも大変ですし、似たようなコードだらけで、プログラム全体がスパゲッティのように絡み合ってしまいます。
オブジェクト指向の世界ではこう考える!
そこで登場するのが、オブジェクト指向の主役である「クラス」と「オブジェクト」です。
- クラス = キャラクターの「設計図」または「職業」 まず、キャラクターの「設計図」を作ります。例えば、「勇者」というキャラクターの設計図(
勇者クラス)を1枚だけ用意します。 この設計図には、勇者なら誰でも持っているべき情報(プロパティ)と、勇者なら誰でもできるべき行動(メソッド)を定義しておきます。- プロパティ(情報・データ): 名前、HP、MP、攻撃力、防御力…
- メソッド(行動・機能): 攻撃する()、防御する()、逃げる()…
- オブジェクト = 設計図から生まれた「具体的なキャラクター」 この「勇者クラス」という設計図さえあれば、私たちは具体的なキャラクター(オブジェクト)を、必要なだけ、簡単に生み出すことができます。
勇者A= 「勇者クラス」から生まれた、名前「アルス」、HP「100」のキャラクター勇者B= 「勇者クラス」から生まれた、名前「ロト」、HP「120」のキャラクター
勇者Aも勇者Bも、同じ「勇者クラス」という設計図から作られているので、同じプロパティとメソッドを持っています。しかし、それぞれ名前やHPの値が違う、独立した存在です。この、設計図から実体化した一つ一つのキャラクターが「オブジェクト」なのです。
このように、オブジェクト指向とは、まず「設計図(クラス)」を作り、その設計図を元に「実体(オブジェクト)」を生成して、それらを連携させてプログラム全体を構築していく、という考え方なのです。
なぜオブジェクト指向が必要なの?大規模開発を楽にする3つのメリット
「設計図と実体に分けるメリットは、なんとなくわかったけど、なぜそこまで重要視されるの?」 その答えは、オブジェクト指向が、特に大規模で複雑なプログラムを開発する際に、絶大な効果を発揮するからです。
メリット1:部品の「再利用」で、開発が圧倒的に効率的になる
一度「勇者クラス」という設計図を作ってしまえば、100体でも1000体でも、新しい勇者を効率的に生み出せます。モンスターを作りたくなったら、「モンスタークラス」という新しい設計図を用意すればOK。このように、部品(クラス)を再利用できるため、開発の手間を大幅に削減できます。
メリット2:役割分担がしやすく、チーム開発に強い
大規模なゲーム開発では、複数のプログラマーが協力します。オブジェクト指向なら、
- Aさんは「キャラクター関連のクラス」を担当
- Bさんは「魔法やアイテム関連のクラス」を担当
- Cさんは「マップやイベント関連のクラス」を担当 というように、役割分担が非常にしやすいのです。それぞれが自分の担当部品に集中できるため、お互いの作業を邪魔することなく、スムーズに開発を進められます。
メリット3:修正や機能追加が驚くほど簡単になる
これが最大のメリットかもしれません。例えば、「全ての勇者の攻撃力を、少しだけアップさせたい」と考えたとします。 もしオブジェクト指向でなければ、100体いる勇者のプログラムを、100回修正する必要があります。
しかし、オブジェクト指向なら、大元である「勇者クラス」の設計図を1か所修正するだけで、そこから生まれた全ての勇者オブジェクトに修正が反映されます。 この「保守・メンテナンスのしやすさ」が、常に変化し成長し続ける現代のソフトウェア開発において、不可欠な要素となっているのです。 さらに、「継承」という仕組みを使えば、「勇者クラス」の能力をすべて受け継いだ、空を飛べる「天空の勇者クラス」を簡単に作ることもできます。
どの言語で使える?オブジェクト指向の学習を始めるための最初の一歩
オブジェクト指向は、特定の言語を指す言葉ではなく、多くのモダンなプログラミング言語で採用されている「考え方」です。
代表的なオブジェクト指向言語
- Java: 大規模な業務システムやAndroidアプリ開発で広く使われる、オブジェクト指向の代表格。
- Python: AI・機械学習やWeb開発で大人気。シンプルながら、強力なオブジェクト指向機能を持つ。
- C++, C#: ゲーム開発やWindowsアプリ開発でよく使われる。
- Ruby, PHP: Webサービス開発で人気。
- Swift, Kotlin: それぞれiOSアプリ、Androidアプリ開発の主要言語。
このように、今をときめく主要なプログラミング言語のほとんどが、オブジェクト指向の考え方を取り入れています。つまり、この考え方を理解することは、現代のプログラマーにとっての必須教養なのです。
初心者大学生のための、オブジェクト指向学習3ステップ
- STEP1:まずは1つの言語の基礎文法をマスターする いきなりオブジェクト指向を学ぼうとせず、まずは
PythonやJavaなど、どれか一つで良いので、基本的な文法(変数、if文、for文など)をしっかり身につけましょう。 - STEP2:「クラス」を作って「オブジェクト」を生み出す体験をする 基礎文法を終えたら、この記事のRPGの例えを真似して、実際に「クラス」を定義し、そこから「オブジェクト」を作ってみましょう。「
Studentクラス」を作り、nameやstudent_idというプロパティ、introduce()というメソッドを定義し、あなた自身や友人のオブジェクトを作ってみる、という簡単な練習でOKです。 - STEP3:身の回りのモノを「オブジェクト」として捉える練習をする 「もし、このスマートフォンをオブジェクトにするとしたら、どんなプロパティ(情報)とメソッド(機能)があるだろう?」 「もし、この講義室をオブジェクトにするとしたら…?」 このように、日頃から身の回りのモノをオブジェクト指向的に捉える「思考トレーニング」をすることで、考え方が自然と身についていきます。
まとめ
今回は、多くのプログラミング初心者がつまずく「オブジェクト指向とは何か」を、RPGの例えを使ってわかりやすく解説しました。
- オブジェクト指向とは、まず「設計図(クラス)」を作り、それを元に「実体(オブジェクト)」を生成して、プログラムを組み立てる考え方。
- なぜ重要かというと、「再利用」「役割分担」「メンテナンス」が容易になり、大規模な開発を効率的に進められるから。
- 現代の主要なプログラミング言語のほとんどが、この考え方を採用している必須教養。
オブジェクト指向は、単なるプログラミングのテクニックではありません。複雑な問題を、整理整頓された「部品」の組み合わせとして捉え、見通しを良くするための、非常にパワフルな「思考の道具」です。
この記事を読み終えたら、ぜひあなたの身の回りにあるもの(例えば、ペン一本でも、椅子一脚でもOKです)を見て、こう考えてみてください。
「もしこれをプログラムの”オブジェクト”にするとしたら、どんな”プロパティ”(情報)と”メソッド”(機能)があるだろう?」
その小さな思考トレーニングが、あなたを一段階上のプログラマーへと導く、最高にエキサイティングな第一歩となるはずです。


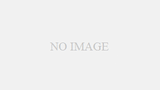
コメント