「最近、授業で “アジャイル開発” って言葉を聞いたけど、いまいちピンとこない…」
「”ウォーターフォール” とか “スクラム” とか、似たような用語が多くて混乱する…」
IT系の学部にいると、必ずと言っていいほど耳にするこれらの言葉。 特にチームで何かを開発する授業や、IT業界のインターンでは必須の知識ですよね。
こんにちは!現役情報系大学生で、このブログ『大学生のためのIT活用ラボ』を運営しているえいとです。
何を隠そう、僕も独学で学んでいたころは、これらの開発手法の違いが全く分からず、チーム開発に挑戦しようとして苦労した経験があります。
でも、安心してください! この記事では、そんな僕の失敗談も交えながら、IT初学者のあなたでも3つの開発手法の本質的な違いがクッキリと理解できるように、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、 「なるほど、そういうことか!」 とスッキリした気持ちで、自信を持って友達や教授に説明できるようになっているはずです。
大学でのプロジェクトや、これからの就職活動でも絶対に役立つ知識なので、ぜひ最後までリラックスして読んでみてくださいね!
まず結論!3つの開発手法の関係性はこれだ!
ごちゃごちゃ説明する前に、まず一番大事な結論から。 アジャイル、スクラム、ウォーターフォールの関係性をざっくり掴んじゃいましょう。
- ウォーターフォール開発: 最初に完璧な計画を立てて、その通りに進めるカッチリ計画型の方法。
- アジャイル開発: 「とりあえず作って、試して、改善」を繰り返す柔軟性重視の考え方。
- スクラム開発: アジャイル開発という考え方を実現するための、超具体的なチーム戦術の一つ。
イメージとしては、開発手法には大きく「ウォーターフォール派」と「アジャイル派」の2つの流派があって、スクラムは「アジャイル派」の中でも特に有名なチームのフォーメーション、といった感じです。
では、それぞれの手法がどんなものなのか、大学生の日常に例えながら詳しく見ていきましょう!
Part 1: まずは基本!カッチリ計画型の「ウォーターフォール開発」
ウォーターフォール開発は、古くからある伝統的な開発手法です。 その名前の通り、水が滝(ウォーターフォール)を上から下に流れるように、工程を順番に進めていくのが最大の特徴です。
大学生の日常で例えるなら…「完璧な構成で挑む卒業論文」
ウォーターフォール開発を一番イメージしやすいのが、卒業論文の執筆です。
- 要件定義: まずは「どんなテーマで、何を明らかにするのか」という論文のゴールを先生としっかり決めます。
- 設計: 次に、そのゴールを達成するための完璧な章立て(目次)を考え抜きます。「第1章 序論」「第2章 先行研究」…のように、書くことすべてを詳細に設計します。
- 実装(執筆): 設計した目次通りに、第1章から順番に書き進めます。
- テスト(推敲): すべて書き終えたら、誤字脱字や論理の矛盾がないか、最初から最後までチェックします。
- リリース(提出): 完成した論文を提出!
この進め方のポイントは、「前の工程が完全に終わらないと、次の工程には進めない」そして「原則、後戻りはしない」という点です。第3章を書いている途中で「やっぱりテーマ変えたいな…」なんてことになったら、もう一度最初からやり直しで大変ですよね。
メリット・デメリット
- メリット
- 進捗が分かりやすい: 全体の計画が最初に決まっているので、「今、全体の何%くらい進んでいるか」が把握しやすいです。
- 品質を保ちやすい: 各工程でしっかり成果物を作ってから次に進むので、一つ一つのクオリティは高くなりやすいです。
- デメリット
- 途中の変更にめちゃくちゃ弱い: 最大の弱点です。開発の途中で「やっぱりこんな機能が欲しい」と言われても、設計からやり直す必要があり、対応が非常に困難です。
- 完成するまで動くものが見れない: 最後のテスト工程まで、実際にどんなものが出来上がるのかユーザーは確認できません。
僕も高校生の時の課題研究で、研究に使う装置を「最初に全機能を詰め込んだ完成品を設計しよう!」と意気込んでウォーターフォール的に進めたことがあります。結果、途中で技術的な問題にぶつかって計画が総崩れに…。結局、締切には、目指していたものよりずっと完成度の低いものを提出することになってしまった苦い経験があります。
Part 2: 今ドキの主流!柔軟性重視の「アジャイル開発」
ウォーターフォール開発の「途中の変更に弱い」という弱点を克服するために生まれたのが、アジャイル(Agile = 素早い、機敏な)開発という考え方です。
大学生の日常で例えるなら…「みんなで改善していく学園祭の模擬店」
アジャイル開発は、学園祭の模擬店で新メニューを開発するプロセスにそっくりです。
完璧な「タピオカミルクティー」のレシピを最初から目指すのではなく、
- 計画: 「とりあえず、今ある材料で一番美味しいと思うミルクティーを作ってみよう!」と小さなゴールを設定。
- 試作(実装): 実際に一杯作ってみる。これが「動くソフトウェア」です。
- 試食(テスト&フィードバック): チームの仲間やお客さん(ユーザー)に味見してもらい、「もっと甘い方が良い」「タピオカは固めがいいな」といった意見(フィードバック)をもらいます。
- 改善: もらった意見を元に、すぐにレシピを改良。
この「計画→試作→試食→改善」というサイクルを、学園祭当日まで何度も何度も素早く繰り返すのがアジャイル開発です。最終的には、お客さんの声が反映された、みんなに愛される最強のタピオカミルクティーが完成するはずです。
メリット・デメリット
- メリット
- 仕様変更に強い: 短いサイクルで開発とフィードバックを繰り返すので、ユーザーの要望の変化に柔軟に対応できます。
- 早くから成果物を確認できる: 開発の早い段階から、実際に動くプロダクトに触れることができます。
- デメリット
- 全体のゴールが見えにくくなることも: 目の前の改善に集中するあまり、「最終的に何を目指していたんだっけ?」となりがちです。
- 進捗管理が難しい: 計画が柔軟に変わるため、「全体の何%進んだ」という明確な指標を立てにくい場合があります。
みんなが普段使っているInstagramやTikTokをイメージしてみてください。新しいフィルターが追加されたり、UIが少し変わったりと、目まぐるしくアップデートされますよね。
これはまさにアジャイル開発の考え方なんです。今のWebサービスの世界では、ユーザーの流行りやニーズは一瞬で変わります。だから、「完璧なものを時間をかけて作る」よりも、「とりあえず新機能をリリースしてみて、反応が悪ければすぐ修正・削除する」という素早い動き方が求められるんですね。
Part 3: アジャイルの優等生!チームで進める「スクラム開発」
「アジャイルが考え方なのは分かったけど、具体的にどうやってチームで動けばいいの?」 その答えの一つが、スクラム開発です。
スクラムは、アジャイル開発を実現するための、最も有名で具体的な「やり方(フレームワーク)」です。
大学生の日常で例えるなら…「ラグビーのように一丸となる模擬店チーム」
名前の通り、ラグビーで選手たちが肩を組んでボールを奪い合う「スクラム」が語源です。チームが一丸となって、同じ目標に向かって進んでいくイメージですね。
先ほどの学園祭の模擬店チームが、スクラム開発を取り入れるとこうなります。
- 役割分担: 「メニュー開発責任者(プロダクトオーナー)」「チームのお世話役(スクラムマスター)」「調理担当(開発チーム)」のように、役割を決めます。
- スプリント計画: まず、「今週1週間(スプリント)で、タピオカの試作と看板のデザインを完成させるぞ!」という短期目標を立てます。
- デイリースクラム: 毎朝5分だけチームで集まり、「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること」を共有する朝礼(デイリースクラム)を行います。
- スプリントレビュー: 1週間の終わりに、完成した試作品や看板デザインをみんなで確認し、フィードバックをもらいます。
- 振り返り: 最後にチームだけで集まり、「今週の動き方、もっとこうすれば良かったね」という反省会(レトロスペクティブ)を行い、来週のスプリントに活かします。
このように、スクラムではチームが効率よく、かつ自律的に動くための具体的なルール(イベントや役割)が決められています。
メリット・デメリット
- メリット
- コミュニケーションが活発になる: 毎日の朝礼や定期的なミーティングで、チーム内の情報共有がスムーズになります。
- チームの生産性が上がる: 短い期間で目標設定と振り返りを繰り返すため、問題点をすぐに改善し、チームとして成長しやすいです。
- デメリット
- メンバーの自主性が求められる: 細かい指示を待つのではなく、チーム全体で目標達成のために何をすべきか考える必要があります。
- 導入が難しい場合も: ルールがしっかりしている分、チーム全員がスクラムを正しく理解していないと、形だけのものになってしまう可能性があります。
Part 4:【一覧表】結局どう違うの?3つの開発手法を徹底比較
ここまで解説してきた3つの開発手法の違いを、一覧表にまとめてみました。 これで頭の中がスッキリ整理されるはずです!
| 比較項目 | ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | スクラム開発 |
| 一言でいうと | 滝のように後戻りしない | 素早く柔軟に対応する | チームでダッシュを繰り返す |
| 計画の立て方 | 最初に全てを完璧に計画 | 全体はざっくり、詳細は短期で | 1~4週間の短期計画を繰り返す |
| 変更への強さ | 弱い(変更は大変) | 強い(変更を歓迎する) | 強い(スプリント単位で対応) |
| 開発スタイル | 一直線に進むリレー | 短距離走の繰り返し | チーム一丸のラグビー |
| 向いているもの | 仕様が固まっている大規模開発 | 仕様変更が多いWebサービスなど | 複雑な問題解決を目指すチーム |
| 例え話 | 卒業論文 | 学園祭の模擬店 | 模擬店チームの運営方法 |
まとめ:大事なのは「使い分け」
最後に、この記事の要点をもう一度おさらいしましょう。
- ウォーターフォールは、最初にゴールを完璧に決めて一直線に進む方法。仕様変更が少ない、大規模なシステム開発に向いています。
- アジャイルは、短いダッシュを繰り返しながら、柔軟にゴールを目指す考え方。ユーザーの要望が変わりやすいWebサービス開発などで主流です。
- スクラムは、アジャイルを実現するためのチームで走る具体的なフォーメーション。チームのコミュニケーションを活性化させたい場合に強力な武器になります。
ここで最も大切なのは、「どれが一番優れている、というわけではない」ということです。 作りたいもの、チームの人数、開発期間など、状況に応じて最適な手法を選ぶ「使い分け」の視点が重要になります。
次への一歩:まずは大学のグループワークで試してみよう!
「開発手法の違いは分かったけど、実際にどうすれば…?」 そう思ったあなたへの、最初の一歩をご提案します。
それは、「次の大学のグループワークで、アジャイルな進め方を意識してみる」ことです。
例えば、4人グループで1ヶ月後にプレゼンがあるとします。 ウォーターフォール的に「各自、担当箇所を締切までにやってきてね」と進めるのではなく、
- 毎週月曜の1限前に「今週のゴール」を決めるミーティングをする。
- 毎日、LINEグループで「今日の進捗」を簡単に報告しあう。
- 毎週金曜の昼休みに「今週の成果と課題」を共有し、来週の計画を修正する。
こんな風に、スクラムの要素を少し取り入れるだけでも、チームの進捗は驚くほどスムーズになるはずです。 ぜひ、あなたのチームで試してみてください!
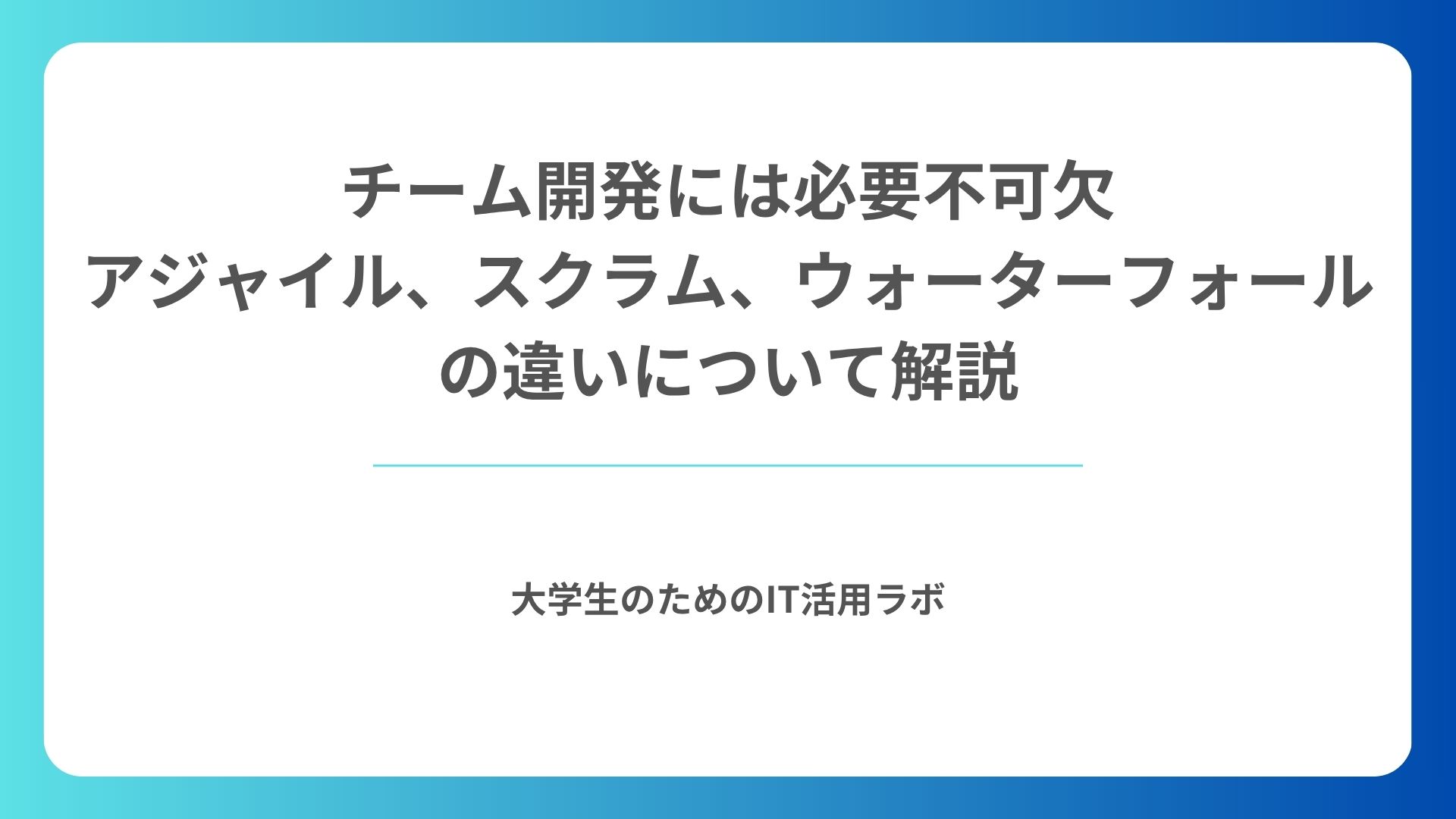
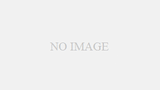

コメント